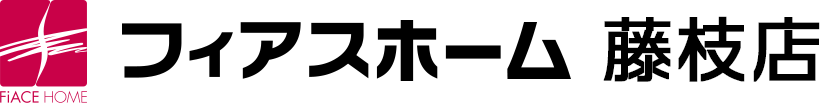家づくりに関する質問やご相談など、
まずはお気軽にお問い合わせください。
ブログ
blog

田舎の古民家から

2025.9.30
こんにちは
工務の村松です
空き家になった田舎の家の片付けをした際に
レトロなものを見つけましたので
紹介をさせていただきます
それがこちら…
工務の村松です
空き家になった田舎の家の片付けをした際に
レトロなものを見つけましたので
紹介をさせていただきます
それがこちら…

分かる方 いらっしゃいますか?
これは「碍子(がいし)」といわれるものです
碍子とは、陶器でできていて
電線を絶縁して固定するための部品です
今のように壁の中に電線を通す「隠ぺい配線」が主流になる前は
電線を壁や天井の表面に露出させて配線する「露出配線」が一般的でした
その際、電線が木や壁と直接触れてショートしないように
電気を通さない陶器製のこの碍子で電線を浮かせて固定していました
これは「碍子(がいし)」といわれるものです
碍子とは、陶器でできていて
電線を絶縁して固定するための部品です
今のように壁の中に電線を通す「隠ぺい配線」が主流になる前は
電線を壁や天井の表面に露出させて配線する「露出配線」が一般的でした
その際、電線が木や壁と直接触れてショートしないように
電気を通さない陶器製のこの碍子で電線を浮かせて固定していました

見た目はレトロですが、今の基準からすると
安全性の面では注意が必要になります
絶縁性能も現代のものと比べると劣るため
古い建物ではリフォーム時に配線の見直しが重要になります
最近では、昔の雰囲気を残したいという理由で
あえてレトロな碍子や露出配線を再現するケースもありますね!
古い建物には、昔の知恵や工夫がたくさん詰まっています
昔の風土に合わせた家づくりの工夫も 勉強になります
昔の知恵も生かしつつ
現代の気候に合わせた 快適な家づくりをしていきたいです
また面白い発見があれば、ブログでご紹介します!
安全性の面では注意が必要になります
絶縁性能も現代のものと比べると劣るため
古い建物ではリフォーム時に配線の見直しが重要になります
最近では、昔の雰囲気を残したいという理由で
あえてレトロな碍子や露出配線を再現するケースもありますね!
古い建物には、昔の知恵や工夫がたくさん詰まっています
昔の風土に合わせた家づくりの工夫も 勉強になります
昔の知恵も生かしつつ
現代の気候に合わせた 快適な家づくりをしていきたいです
また面白い発見があれば、ブログでご紹介します!
Possted by
プロジェクトマネージャー
村松 裕子

打ち合わせから完成まで、一つひとつの工程に寄り添いながら、おうちづくりをサポートさせていただきます。
「頼んでよかった」と思っていただけるよう、現場管理とお客様との連携を大切にし、安心して進められる家づくりを心がけています。
疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでも遠慮なくご相談ください。
スタッフ
アーカイブ
スタッフ
アーカイブ